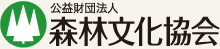「木の宿場」で森をきれいに / 山仕事と商店街に新たな繋がり
「疎開保険」や「森のようちえん」「森林セラピー」「智頭(ちづ)野菜新鮮組」……ユニークな地域おこしのアイデアが、「緑の風が吹く疎開の町・鳥取県智頭町」を支えている。だが、「智頭杉」ブランドの伝統的林業地としては、町の面積の93㌫を占める森林が元気にならなければ、本当の地域おこしは実現しない。そこで、木材の値段が下がり金にならない林業から離れている町民の関心を、再び山に呼び戻し、森に手を入れ、それをさらに町の商店街の活性化に繋げよう、という社会実験が、2010年から始まった。名付けて智頭町「木の宿場(やど)」プロジェクト。
1㌧6000円で晩酌を
「木の宿場」プロジェクトは、町政に町民の声を反映するための組織「百人委員会」の農林部会で提案され、実施のために「実行委員会」がつくられた。間伐材や林地に放置された残材などを山から搬出し、集積場(土場)に持ってきた人には、誰でも、1㌧当たり6000円相当の「杉小判」と呼ばれる地域通貨を発行する、というのが基本的な仕組み。1枚1000円の「杉小判」は、プロジェクトに加盟登録している町内の商店で、現金並みに通用する。
例えば、普段は会社勤めをしている町内のあるお父さんが、親から受け継いだ山林を持っているとしよう。これまで、管理は森林組合にまかせ、自分では原木を市場に出荷した経験のない「素人山主」の1人だった。「木の宿場」プロジェクトに登録をしてからは、会社が休みの週末、軽トラックにチェーンソーを積んで、山に向かう。切り捨て間伐の材が、あちこち転がっている。
搬出する材は、長さ50 ㌢以上で、細い方の口径5㌢以上が決まり。この程度の大きさなら、倒れている木を適当な長さに切って担ぎ、荷台に積んで森から持ち出すことができる。山から程遠からぬ町内3カ所の土場のうち、指定された場所に材を持ち込むと、自分で長さと口径を測り、伝票に記入する。これで体積を割り出し、さらに重さに換算すると、「杉小判」の発行だ。軽トラで3回ほど往復すれば、5、6千円分にはなる。
ひと汗かいて、日暮れ時。家に軽トラを置いて一杯……と、街中の居酒屋へ。そこは、「木の宿場」加盟店の一つ。お客が代金として支払った「杉小判」を、店側は、実行委員会窓口で現金化できるし、ほかの加盟店での買い物に使うこともできる。加盟登録商店は、地域おこしの観点から地元のみ。全国チェーンの大型店などは含まれない。
「杉小判」の支払いは、1000円単位、使用期限あり、というところが、買い物の思案のしどころ。「おつりなしなら半端だから、もう1皿追加! 運動不足を解消して小遣いもらったようなものだし、ま、いいか」という期待を込めてか、「木の宿場」のキャッチフレーズは「軽トラとチェーンソーで晩酌を!」だ。
集まった材は、「杉小判」を現金と交換する資金にするため、実行委員会がまとめて月1回、チップ工場へ原料として出荷する。トン当たり3000円が今の相場。「杉小判」のトン当たり6000円に届かない分は、2000円を町が補い、1000円分は、海と山の連携を模索する鳥取の漁港のNPO「賀露(かろ)おやじの会」などが協力して補塡(ほてん)する。「賀露おやじの会」は、智頭町の間伐材で作った「組手什(くでじゆう)」と呼ばれる組み立て家具のキットを販売して、売り上げの5㌫寄付している。
2010年10月、1カ月間のプロジェクト試行がスタートした日には、土場の前に、材を運びこむ軽トラックが列をなした。試行期間を通じ、出荷者は29人、登録商店が26軒、197㌧の木材が集まり、85万円の「杉小判」が発行された。2011年には、規模を拡大して5月から11月まで行われ、暫定集計で出荷者39人、登録商店40軒、480㌧の木材を収集し、290万円の「杉小判」を発行する結果を残した。2次流通まで入れると、智頭町のGDPを数百万円分押し上げる効果があったかもしれない。
プロジェクトが動き出して、出荷者からは「山がきれいになった」「山仕事を一緒にやる仲間ができた」など、商店からは、「初めて来るお客さんが増えた」「杉小判を話題にお客さんと会話が弾んだ」などの感想が出ているという。
外の風と善意のシステムで進展
「木の宿場」にはモデルがあった。高知県の仁淀川(によどがわ)流域の林地残材収集運搬システムだ。NPO「土佐の森・救援隊」が、独立行政法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」の木質バイオマス活用プラントに向けて構築し、運び込んだ木材はNEDOが買い上げる。しかし、そのような施設のない智頭町では、どうするか。
実行委員会は、役場や町民はもちろん、外部の研究者、NPOなどに参加してもらい知恵を借りた。その1人が、鳥取大学地域学部非常勤講師の丹羽健司さんだ。丹羽さんは、愛知県の矢作川(やはぎがわ)流域で、市民参加型の森林調査「森の健康診断」を発案し、全国24都道府県での取り組みにまで広めた「矢作川水系森林ボランティア協議会」の代表でもあった。「土佐の森・救援隊」に感動し、各地にその方式を広める活動もしてきた。智頭町の事情に合わせて仕組みを具体化し、運営のコーディネーター役を果たしている。
丹羽さんによれば、「NEDOのような大きな受け皿がなくても大丈夫」だという。「中学校区ぐらいの小さな単位で実施すれば、かえって性善説をもとにした身軽な運営ができる」。「木の宿場」の肝心な部分は、ほとんど自己申告制度だ。互いの顔の見える関係の中では、木の長さや口径を伝票に書き込む際、過大に申告するような悪さは起きない。むしろほとんどが過小申告という。管理のための人手も省略できる。「志~材」とよばれる「杉小判」に交換されない寄付の材が、いつの間にか土場に積み上がり、運営費を助けている。遠くの安い大型店を利用していた人が、山仕事と「杉小判」を通じて地元の商店となじみになり、市場経済の原理を超えて、新しい繋がりが生まれる。プロジェクトに参加した町民は、「杉小判を使うことが仲間づくりだと気付いた」ともいう。
林業の不振に悩む全国の自治体にとって、森の活用は共通の課題だ。新しい年、「森を生かす」智頭町の試みがどのように進展するかは、日本の地域の未来に深くかかわっている。
(グリーンパワー2012年2月号から転載)